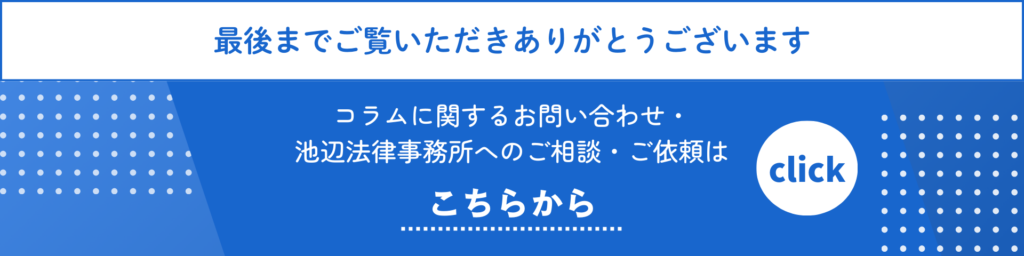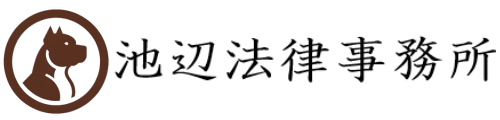どこからがカスハラ?東京都ガイドラインから見る「代表的な行為類型」

「お客様は神様です」という言葉は、かつて日本のサービス業を象徴するフレーズでした。しかし現代において、その精神が行き過ぎた結果、働く人々に過剰なストレスや負担を強いるケースが増えています。これが「カスタマーハラスメント(略してカスハラ)」と呼ばれる問題です。
顧客からの理不尽な要求や暴言、執拗なクレームなどにより、現場で働く人たちが心身にダメージを負い、離職につながるケースも少なくありません。こうした背景のもと、東京都は令和6年に「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定し、企業や事業者が取るべき対応を明示しました。これは、東京都外の企業にとっても、大いに参考になるものです。
本コラムでは、どういった行為がカスハラにあたるのかを把握するため、上記ガイドラインを根拠に、「カスハラの代表的な行為類型」について、わかりやすくご紹介します。
パターン1:妥当性を欠く要求
カスハラとして典型的なものは、妥当性を欠く要求です。
カスハラかどうかを判断する第一歩は、「その要求が妥当なものかどうか」です。つまり、商品やサービスに本当に瑕疵があったのか、そしてその要求が因果関係に基づいたものであるかを検討する必要があります。
1
会社が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
商品やサービスに問題がないにもかかわらず、顧客が不満を理由に過剰な要求をするケースは、典型的な「妥当性を欠く要求」となります。たとえば以下のような例が挙げられます。
このような要求は、顧客の主観や都合に基づいており、商品やサービスの品質・提供に問題がない限り、会社が応じる義務はありません。
2
要求内容が、会社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
そもそも、会社が提供している業務範囲とは全く無関係な事柄について、顧客が何らかの責任を転嫁しようとするケースもあります。これも「妥当性を欠く要求」に該当します。具体的な例としては以下のようなものがあります。
これらの要求は、会社の対応可能な業務範囲を超えており、実質的には理不尽な要求に該当します。
こうした妥当性を欠く要求は、ただ平穏に求めるだけでは必ずしもカスタマーハラスメントと断定されるものではありませんが、後述するように、暴言・威圧的態度・執拗な要求などの要素と結びついた場合、カスハラとして認定される可能性が高まります。
パターン2:要求手段・態様が不相当な場合
顧客の要求内容が妥当であったとしても、それを実現する手段や態度が社会通念を逸脱していれば、それは明確なカスタマーハラスメントです。東京都のガイドラインでは、「違法または社会通念上不相当」とされる手段・態様として、以下のような類型が挙げられています。
| ①身体的な攻撃 | ・物を投げる、唾を吐くなどの行為 ・殴る、蹴るなどの暴力行為 これらは、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)などの刑事罰に該当するおそれがあり、カスハラとしてだけでなく、即座に法的対応を検討すべき行為です。 |
| ② 精神的な攻撃 | ・会社やその親族に対して危害を示唆するような発言 ・大声での執拗な叱責 ・人格を否定するような言葉遣い ・多数の前での侮辱的な発言 これらは、脅迫罪(刑法第222条)、恐喝罪(刑法第249条)、名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)などに該当する可能性があり、従業員の精神的負担も非常に大きくなります。 |
| ③ 威圧的な言動 | ・声を荒らげる、机を叩く、にらみつける ・話を遮って威圧的に要求を通そうとする ・会社の発言の揚げ足を取り、責め立てる このような言動は、脅迫罪や威力業務妨害罪(刑法第234条)に抵触する可能性があり、恐怖やストレスを感じる典型的な状況です。 |
| ④ 土下座の強要 | ・謝罪の手段として従業員に土下座をさせようとする このような行為は、単なる侮辱にとどまらず、強要罪(刑法第223条)に該当するおそれがあり、極めて問題のある要求態度とされます。 |
| ⑤ 執拗な(継続的な)言動 | ・長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す ・要求内容を変えずに何度も電話をかける これは、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪(刑法第233条)にも該当しうる行為であり、心理的負担が蓄積しやすい危険なタイプのカスハラです。 |
| ⑥ 従業員を拘束する行動 | ・店舗や事業所に長時間居座る ・退去を求められても正当な理由なくとどまり続ける ・個室に従業員を呼び出し、長時間にわたり要求を繰り返す これらは、監禁罪(刑法第220条)、不退去罪(刑法第130条)、さらには業務妨害罪にも該当する可能性があります。物理的・時間的に従業員を拘束する行為は、法的にも非常に重大な問題です。 |
| ⑦ 従業員への差別的な言動 | ・人種、職業、性的指向、性別などに対する侮辱的発言 例として、「男のくせに」「外国人にはわからないだろう」といった発言も、状況によっては名誉毀損罪や侮辱罪として扱われる可能性があります。多様性と人権が尊重される現代社会において、極めて不適切な言動です。 |
| ⑧ 従業員への性的な言動 | ・わいせつな発言や身体への接触 ・従業員へのつきまといやストーカー行為 これらの行為は、不同意わいせつ罪(刑法第176条)やストーカー規制法違反として処罰される可能性があります。特に、接客現場において見過ごされやすい問題であり、企業は早期対応が求められます。 |
| ⑨ 従業員個人への攻撃や嫌がらせ | ・服装や容姿についての中傷 ・SNS上で従業員を名指ししての批判 ・顔写真や名札の無断撮影・公開 このような行為は、名誉毀損罪やプライバシー侵害といった観点からも重大であり、SNS時代におけるカスハラの新たな形といえます。 |
以上のように、要求の内容だけでなく、その伝え方や態度もカスハラか否かの重要な判断基準となります。従業員の尊厳や安全を脅かすような言動は、たとえ一時的な感情から出たものであっても、企業としては毅然とした対応が必要です。

パターン3:妥当性があっても過度な要求はNG
最後に、要求内容の妥当性と、要求を実現するための手段・態様がアンバランスである場合も、カスハラの類型の1つです。
例えば、「商品に不備があったので補償を求めたい」という一見正当なケースがあります。しかし、求める補償の程度が社会通念に照らして過度である場合は、やはりカスハラとみなされる可能性があります。以下に、ガイドラインが示す典型例を紹介しつつ、実務上の対応の視点を加えて解説します。
1
過度な商品交換の要求
商品に瑕疵がある場合の対応として、同等品との交換を求めるのは一般的な消費者権利の一つですが、それが常識を超えるような要求になると問題です。
このようなケースでは、もはや補償ではなく「過剰な見返りの強要」となっており、従業員にとっても現実的対応が困難となります。
2
過度な金銭補償の要求
実際に損害が発生した場合でも、その程度や因果関係に即した補償額が求められるべきです。これを大きく逸脱した金額を求める行為は、カスハラに該当し得ます。
こうした要求は、実際の損害をはるかに上回るものであることが多く、企業としても毅然と対応する必要があります。
3
過度な謝罪の要求
謝罪自体はサービス業において一定程度行われる行為ですが、その手段や対象、頻度において過剰な要求がなされる場合には、従業員の尊厳を損なう危険があります。
謝罪の内容が合理性や必要性を欠いており、もっぱら「謝らせること」そのものを目的とした場合、それはもはや謝罪ではなく精神的圧力や見せしめに近くなってしまいます。
4
その他、不可能な行為や抽象的な行為の要求
従業員が対応し得ないこと、あるいは対応方法が不明瞭な要求もまた、現場を困らせる典型です。
これらの要求は、どのように対応しても顧客の納得を得られず、延々とクレームが続く原因にもなり得ます。従業員に「終わりの見えない苦痛」を与える行為として、深刻なカスハラと位置付けられます。
企業が取るべき対応とは?
カスタマーハラスメントの防止は、単に従業員の負担を減らすだけでなく、企業全体の労働環境やブランド価値を守るうえで極めて重要です。
- ハラスメントに該当するかどうかの判断基準を明確にする。
- 従業員向けに対応マニュアルや教育研修を整備する。
- 実際にカスハラが発生した場合に相談できる体制(上司・法務・外部窓口)を確立する。
以上のことが、安心して働ける職場づくりにつながります。
カスハラについては、以下のコラムでも取り上げております。よろしければこちらもご覧ください。