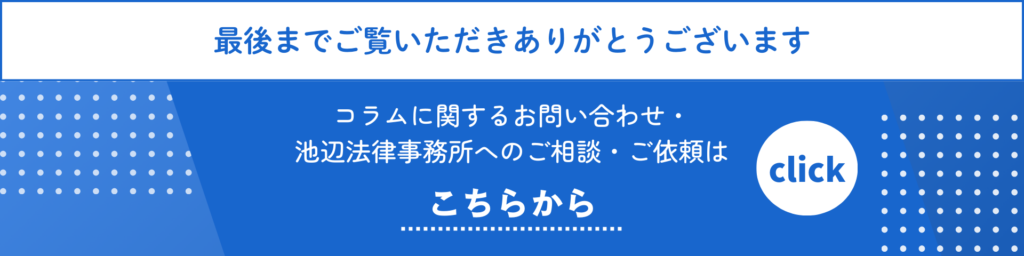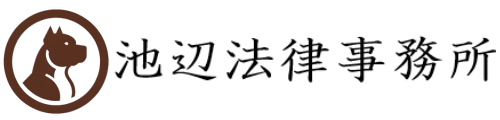裁判で「事実」と認められるまで──証拠と裁判官の思考プロセス
裁判において、真実はどのように見極められるのか。
「裁判で真実が明らかになる」と考える人は多いでしょう。ですが、もし真実がいつも簡単に明らかになるのであれば、私を含めた弁護士が汗をかいて証明に力を尽くす必要はありません。
実際の民事裁判では、全知全能の「神」が真実を直接見抜くわけではなく、限られた証拠や証言しか持たない裁判官が、原告と被告どちらの主張が事実かを「認定」しなければなりません。
では、裁判所は何を基準に「事実」と認めているのでしょうか?
本コラムでは、その実態に迫りながら、証言が信用されるかどうかを分けるポイント、さらに弁護士が用いる証言を崩す技術までを、分かりやすく解説します。
1.民事裁判で求められる証明とは何か
まず、誤解されがちですが、民事裁判で求められる「証明」とは、数学や自然科学のように、すべての可能性を完全に排除した証明ではありません。裁判では、いわゆる100パーセントの証明までは求められていないのです。
最高裁判所は、「ルンバール事件」(最二小判昭和50.10.24)という有名な事件で、次のように述べています。
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく(中略)特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
このように、民事裁判では「高度の蓋然性」があれば証明をしたことになり、あくまでも通常人(一般人)が疑いを差し挟まない程度の確信があれば良いとされています。
最高裁は、民事裁判での証明について、一点の疑義も許されないわけではないし、自然科学的証明ではない、と明言しています。この前提を知らなければ、裁判でどのように真実が認定されているのか、その理解を誤ってしまうでしょう。
裁判になるような事件は、原告と被告のどちらが本当のことを言っているのか、微妙なケースも少なくありません。したがって、裁判において完璧な証明を求めることは難しく、「高度の蓋然性はあるか」という観点から真実が判定されているのです。

2.信用できる供述とは何か
そして、高度の蓋然性に達するかどうかは、提出された証拠の「信用性」(どの程度信用できるか)に大きく左右されます。
民事裁判では、契約書などの書面の証拠が最も重視されます。しかし、すべての事実を必ずしも書面で証明できるわけではありません。書面の証拠がなく、人の記憶や体験に基づく「証言」に頼らざるを得ない場面も、民事裁判では多くあります。
民事裁判では、当事者双方の証人が真逆の証言をすることも珍しくありません。
そのような場合、裁判官は次のような視点から、どちらの証言が信用できるのか、つまり証言の信頼性を見極めています。
① 「動かし難い事実」と整合するか、しないか
② 経験則に反する供述ではないか
③ 矛盾を含む供述ではないか
例えば、防犯カメラに映っていない場所に「そこにいた」と証言する場合は、動かし難い事実と整合しないとして、信用できないと判断されます。また、「特別な条件で合意したが、そのことは書かずに契約書を作った」といった話は、経験則に反する、つまり常識的に考えて信じがたいものとされ、供述の信用性に疑問が生じます。
裁判官は、証言にこのような問題が含まれていないかどうかを慎重に検討し、それによって証言をどこまで信頼できるかを判断していきます。
3.弁護士は供述のほころびをどう突くか
実は、技術に長けた弁護士は、相手方の証人を尋問する際、意図的に上記の①②③に該当する供述をするように質問を組み立てます。
複数の質問を通じて供述の流れをコントロールし、例えば相手方の証人に、客観的証拠と食い違う発言をさせたり、経験則に反する不自然な話をさせるよう誘導するのです。これにより、その証言の信憑性を揺るがせることができます。
弁護士は、証人尋問の際、常にリアルタイムで頭を回転させています。
相手方の証人は今どんな気持ちでいるのか、思考が明晰なのか、それとも緊張や疲労で思考が鈍っているのか、こちらに迎合的なのか、それとも敵対的なのか。
そういった状況を見極め、それに合わせて質問を柔軟に変化させていきます。
ときには法廷で、証人が感情的になり、「相手方は極めて異常な行動をとった、信じられない人間だ」といった趣旨の証言をすることがあります。
しかし、これに具体的な裏付けが伴わない場合、かえって「経験則に反する供述」とみなされ、証言の信用性を自ら損なう結果になりかねません。
こうした心理状態に相手方証人を追い込むため、証人を挑発するテクニックを駆使する弁護士もいます。
4.「異議あり!」は万能か(弁護士の誘導テクニック)
それでは、相手方の弁護士の技術によって、味方側の証人がまずい発言をしようとしているときに、「異議あり!」と割って入り、質問の流れを妨害することは有効な訴訟戦術といえるでしょうか。
まれに有効である場合もありますが、異議に説得力のある理由がない場合、裁判官は「割って入らなければ、まずい状況だったということか。この証人は信用できないかもしれないな。」と考えてしまう可能性があります。ですから、異議を提示することは、決して万能な対抗手段ではありません。
また、相手方の弁護士の質問に答えないことも、誠実な証言態度ではないとみなされ、裁判官の心証にマイナスの影響を与えることになります。
技術のない弁護士は、単に相手を攻撃するだけで終わってしまうことが多いのに対し、優れた弁護士は、相手側の証言を不自然なもの、信用できないものへと少しずつ誘導する技術を持っています。そして、こうした誘導は、異議や沈黙によって防ぐことは困難なのです。

5.裁判官はどこまで「真実」に迫れるのか(まとめ)
裁判は、絶対的な真実が明らかにされる場ではなく、限られた証拠をもとに「高度の蓋然性」があるかどうかを見極める場だといえます。そのためには、証拠の吟味、特に供述の信用性を見極めることが重要です。
法律の世界には、歴史的に培われてきた、真実を見抜くための論理と判定方法があり、それが裁判官の最大の武器となります。
そして、そのことを知っている弁護士たちは、なんとか裁判官の事実認定を顧客に有利にしようと、法廷の中心で攻防を繰り広げているのです。
こうして積み重ねられた判断が、やがて「裁判上の真実」として形作られていきます。
最終的に勝敗を分けるのは、真実そのものではなく、証拠と論理、そしてその組み立て方なのです。