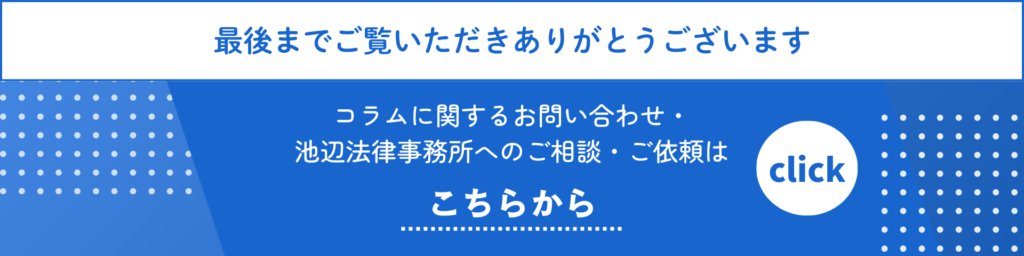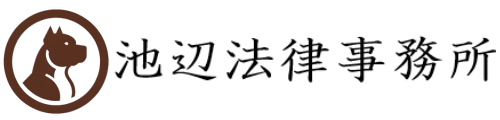新たな最高裁判例が示す「事業場外労働のみなし労働時間制」の限界とは?
外勤に適用されうる「事業場外労働のみなし労働時間制」
オフィスの外で業務に従事する労働者に対しては、一定の場合、労基法は「事業場外労働のみなし労働時間制」を認めています(労働基準法第38条の2)。
「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、労働者が、労働時間の全部または一部を事業場外で行い、会社が労働時間を算定することが難しい場合に適用される制度で、この制度によって、所定の労働時間、労働したものとみなされるため、労働時間の管理が柔軟になります。
この制度は、事業場外(オフィス外)で業務を行う際に、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な業務が対象となります。
例えば、営業職や出張中の労働者は、事業場外での業務遂行中に細かい指示を受けることが少なく、自身の裁量で業務を進めることが多いため、労働時間の把握が難しい場合が多いです。このような状況では、「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用され、所定労働時間を働いたものとみなされます。
一方で、この制度が適用されると、所定労働時間ちょうどの労働とみなされて残業代が出ないため、この制度の適用が無効であるとして、裁判で争われるケースが後を断ちません。
事業場外であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合は、この制度の適用ができないのです。例えば、使用者がリアルタイムで業務の進行を管理・指示している場合や、アプリなどで労働時間を正確に把握できる状況では、労働時間の管理と算定が可能です。このようなケースでは、みなし労働時間制の適用は認められません。
「事業場外労働のみなし労働時間制」は、労使の双方にとって有用な制度ですが、トラブルを避けるために、その限界について知っておく必要があります。
本コラムでは、この制度に関して、2024年4月に出ました、新たな最高裁判例の解説、そして実務における適用限界について詳しく解説します。

「事業場外労働のみなし労働時間制」に関する、新たな最高裁判例
協同組合グローブ事件(最判R6.4.16)が、事業外労働のみなし労働時間制について判断した、新たな最高裁判例です。
この事件は、外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が原告となったものです。
原審である高等裁判所は、業務日報を通じて「労働時間を把握することが可能である」ので、事業外労働のみなし労働時間制の適用は無効であると認定しました。
具体的には
- 労働者の業務である巡回、訪問の頻度がある程度、定まっており、労働者の選択し得る幅には限界があったこと
- 業務後に業務日報を提出することが求められ、その日報には、具体的な始業時間、終業時間、行き先、面談者等が記載されていたこと、これらの内容は支所長が審査をし、正確性について実習実施者等に確認することも可能だったこと
- さらに、携帯電話を利用して業務の指示や報告を行う態勢が整っていたこと
以上の理由から、労働時間の把握は十分に可能であったと判断されました。
しかし、最高裁はこの控訴審の判断を覆しました。
最高裁は、
- 労働者の業務が、訪問指導や技能実習生の送迎、急なトラブルの対応など多岐にわたること
- 労働者自身が訪問の予約を行うなど、具体的なスケジュールを自ら管理し、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや、自らの判断で直行直帰することもあり、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったこと
- 業務日報の内容の正確性についても、労働者に確認する方法の、現実的な可能性や実効性が明らかでないこと
と指摘し、控訴審判決を破棄しました。
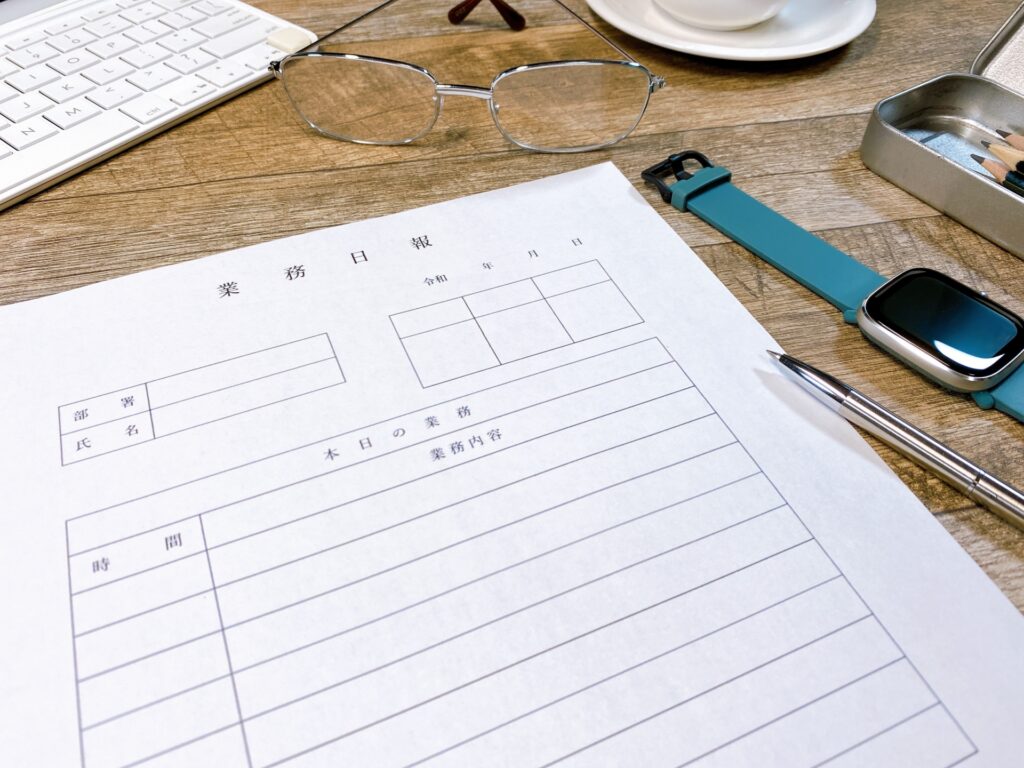

「事業場外のみなし労働時間制」の限界はどこにある?
このような最高裁の判断があったのですが、「事業場外のみなし労働時間制」の限界をさらに理解するために、より以前の判断である、阪急トラベルサポート事件(最判H26.1.24)を見てみましょう。
この事件では、海外旅行の派遣添乗員について、事業場外のみなし労働時間制の適用が否定されました。
「労働時間を算定し難い」にあたらない、と判断した理由としては、
- 添乗員の業務は、旅行日程において日時や目的地等が具体的に決まっており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲、及び、その決定に係る選択の幅は限られている
- 会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で変更を要する事態が生じた場合には、携帯電話で連絡をとり個別の指示をするものとされていた
- 旅行日程の終了後は、内容の正確性を確認し得る添乗日報によって、業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされていた
ことが挙げられていました。
この事件と、新しい最高裁判例の事件は、「日報があった」点では共通していますし、その影響からか、控訴審は業務日報の存在を重視して判断をしました。また、会社と労働者は携帯電話により連絡が可能であったという点でも、両事件は共通しています。
しかし、新しい最高裁判例は、そのような控訴審の判断を否定しました。
このことから、「事業場外のみなし労働時間制」の適用ができるか否かについては、日報があることや、携帯電話で連絡が可能である、ということは、決定的な要素ではないようです。
むしろ、事業場外において労働者が業務実施をするにあたり、裁量の幅があって、そのスケジュールや不測の事態への対応等につき、細かいことは任されているか、といった要素が重要視されているように思えます。確かに、労働者にスケジュールなどの主導権があるならば、会社は労働時間を正確には算定しづらいです。
また個人的には、「事業場外のみなし労働時間制」の適用により、実際には超過労働が生じているが、所定の労働時間働いたものとみなされることがあったとしても、その反面、労働者が会社からの細かな監視を免れていたり、労働者にスケジュールなどの裁量があるのであれば、労働者にとっても良し悪しであるから、そこまでアンフェアでもないのでは、と判断しています。

まとめ
令和3年3月に厚生労働省より発出された、**「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」**でも、会社側からの拘束が緩やかな場合、テレワークについて「事業場外のみなし労働時間制」の適用ができるとされています。
確かに、会社の細かな監視が及ばず、また、労働者側にスケジュールや、仕事の順番について裁量があるテレワークについては、検討してきた判例に照らしても、「事業場外のみなし労働時間制」の適用があって良いところと思えます。
このように、「事業場外のみなし労働時間制」の適用の可否については、通信機器により会社と労働者がつながっていたり、業務報告や日報が義務づけられていたとしても、それらは決定的な要素ではなく、具体的な業務の実施内容から、労働者の裁量の程度も考慮して、制度適用の可否を考えていく必要があります。
【参考リンク】
- 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
- 最高裁Webサイト 最判R6.4.16(協同組合グローブ事件)
- 最高裁Webサイト 最判H26.1.24(阪急トラベルサポート事件)
- 池辺法律事務所「労働法コンサルティング」